「SEOと更新頻度って関係あるの?」
「更新すればするほど、SEO効果が高まるの?」
上記のような疑問をお持ちではないでしょうか?
Webコンテンツは、一度作るだけでユーザーを獲得し続けられるものではありません。安定して集客し続けるためには、何度も更新してコンテンツの質を高く維持する必要があります。
本記事ではSEOと更新頻度の関係や、SEO効果の高い更新の方法について詳しく解説します。ぜひ最後までご覧いただき、SEOに強いWebコンテンツの運営に役立ててください。
【本記事でわかること】
- 更新頻度とSEO効果の関係
- コンテンツ更新で得られるSEO効果
- SEO効果を高める更新の具体策
- SEO効果の出やすい更新頻度の目安

更新頻度はSEO評価に関係するが、質の低い更新方法だと無意味

結論からいうと、Webコンテンツの更新頻度はSEO評価に関係します。ただし更新頻度が高いからといって、SEO効果も必ず高くなるわけではありません。
更新して記事の質が上がって、はじめてSEO効果も高くなります。
逆に以下のような質の低い更新をしても、プラスには働きません。
▼質が低い更新方法の例
- コンテンツの内容を変更せず最終更新日だけ更新する
- ユーザーのニーズに合わない無駄なコンテンツを増やす
質の低い更新をくり返してもSEO効果は無いどころか、逆効果になる可能性もあるのでご注意ください。
コンテンツを更新することで得られるSEO効果

Webコンテンツを更新することで、主に下記の2つのSEO効果が得られます。
上記それぞれについて、以下で詳しく解説します。
検索エンジンから高評価を得られる
コンテンツは適切な更新によって、検索エンジンから高評価を得られます。その主な理由は、以下の2つです。
- ユーザーのニーズに合わせて更新していると判断されやすいから
- 情報の鮮度や話題性の高いコンテンツを上位表示させるアルゴリズムになっているから
つまり、ユーザーのニーズに合わせてコンテンツを正しく更新すると、検索エンジンからの評価も高くなります。
検索エンジンから高評価が得られれば上位表示され、ユーザーの流入を増やせます。
ユーザーから信頼される
コンテンツを適切にアップグレードすれば、ユーザーからも信頼されやすいです。ユーザーは常に新しい情報を求めており、更新したばかりのコンテンツは情報も最新であると判断されます。
たとえば最終更新日が昨日のサイトAと、10年前のサイトBがあった場合、ユーザーにとって信頼に足るのはいうまでもなく情報が最新のサイトAです。
ユーザーからの信頼が得られれば、再訪も期待できます。常にユーザーのニーズを意識しながら、コンテンツを運営しましょう。
SEO効果の高い更新をするために押さえておくべきポイント

コンテンツを更新する際、SEO効果をより高めるために押さえておくべきポイントは下記の2点です。
以下で詳しく説明します。
更新頻度よりもコンテンツの質が重要
WebコンテンツのSEO効果を高めるためには、更新頻度よりもまずは質を重視しましょう。検索エンジンはユーザーのニーズに合った有益なコンテンツを評価するからです。
逆にいくら更新頻度が高くても、質の低いコンテンツを量産してしまうとかえって評価を落とすこともあります。質が低いコンテンツとは下記のようなものです。
- 情報が古い
- 情報が誤っている
- ユーザーのニーズに合致していない
- 競合コンテンツと同じような内容を紹介している
- 誤字脱字が多い
- 文章が読みづらい
コンテンツを更新する際は常にユーザーのニーズを意識し、ユーザーにとって有益な情報を提供するようにしましょう。
ジャンル・内容によって更新頻度を調整する
Webコンテンツはジャンルや内容によって更新頻度を調整しましょう。
たとえば情報の鮮度が重視されるジャンルでは、更新頻度が高いほどSEO効果も高くなります。
▼情報の鮮度が重要なジャンルの例
- ニュース情報
- 芸能情報
- トレンド情報
- 商品・サービス情報
話題性やトレンド性の強いジャンルでは、ユーザーは常に新しい情報を求めています。たとえば最新のニュース情報を知るために検索した場合、10年前の記事では情報が古すぎて検索上位に表示されません。
とくに医学や法律、金融といったYMYLの対象ジャンルは、定期的に情報がアップデートされるため更新による最新かつ正確な情報の提供が必要です。長く更新を怠れば、古い情報を紹介している記事とみなされてしまうでしょう。
逆に慣用句や敬語の意味、物の由来など、意味や内容がすぐに変わらないジャンルは、更新頻度よりもコンテンツの質が優先されます。
情報の鮮度と質、どちらがユーザーにとって重要かを考慮し、更新頻度を調整しましょう。
SEO効果を高める更新方法

SEO効果の高い更新をするポイントが分かったところで、SEO効果を高める具体的な方法について紹介します。コンテンツの質を高める更新方法は以下の6つです。
- 検索上位のコンテンツとの差分を見てリライトする
- 情報が古いコンテンツのリライトをする
- 低品質なコンテンツを削除する
- 似たテーマのコンテンツをまとめる
- 質の高いコンテンツを新規作成する
- コンテンツに最終更新日を記載する
検索上位のコンテンツとの差分を見てリライトする
リライトの際は検索上位の競合コンテンツと自社コンテンツを比較し、自社に足りない要素を分析しましょう。検索上位のコンテンツを分析すれば、検索エンジンがどのようなコンテンツを評価しているのかを具体的に把握できるからです。
競合コンテンツと比較する際は、下記の4点を意識しましょう。
- 情報の量・質:情報量は足りているか?情報は最新で正確か?
- ニーズへの回答:ターゲットとなるユーザーのニーズを満たせているか?
- 独自性:他には無い、オリジナルな情報を盛り込めているか?
- 見やすさ:視覚的にわかりやすいコンテンツになっているか?
これらのポイントを意識して自社コンテンツを改善することで、検索エンジンからの評価を高められます。
▼競合コンテントとの差分を埋めるためのリライト例
| 競合に劣っている要素 | 解決策 |
|---|---|
| 情報量が不足している | ・欠けている内容を追加する ・周辺情報を追加する ・独自の視点や分析を加える |
| 情報量は多いが読みづらい | ・情報を整理する ・箇条書きや表を活用する ・画像や動画を挿入する |
リライトのテクニックは以下の動画でも解説しているので、こちらも参考にしてください。
情報が古いコンテンツをリライトする
情報が古いコンテンツはリライトをしてSEO効果を高めましょう。情報が古いコンテンツはユーザーにとって有益ではないとみなされ、評価が下がる可能性があります。
たとえばある商品の値段について検索したときに、5年前の価格を教えられても当然役には立ちません。
情報は常に変化しているため、執筆当初は正しい情報であっても時間が経てば間違った情報になる可能性があります。常に情報をアップデートして、正しい内容にリライトしましょう。
低品質なコンテンツを削除する
質が低いコンテンツは無理にリライトせず、削除するだけでSEO効果が高まる可能性があります。
検索エンジンはユーザーにとって有益なコンテンツを評価し、そうでないものは評価しません。低品質なコンテンツの割合が多いと、同一サイト内にある他のコンテンツの評価も一緒に下がる恐れがあります。
ただし、コンテンツを削除しすぎるとサイト全体の構成が崩れ、かえって評価が下がる可能性もあります。検索順位やアクセス数などを参考にしながら、本当に削除する必要があるコンテンツか判断しましょう。
似たテーマのコンテンツをまとめる
テーマが似ているコンテンツは1つにまとめましょう。
サイト内に同じような内容のコンテンツが複数あると、検索エンジンの評価が分散して低評価につながる恐れがあります。
例として、
- ブログの収益化について
- ブログで稼ぐ方法について
という2つのコンテンツを同じサイトで公開したとしましょう。両者はテーマが似ているため、内容を差別化できていない限り重複コンテンツとみなされ評価が下がってしまう恐れがあります。
似たテーマの情報を1つにまとめると、ユーザーにとってもわかりやすく読みやすいコンテンツになります。コンテンツは無闇に制作せず、サイト全体の構成を考えて重複コンテンツが生まれないようにしましょう。
質の高いコンテンツを新規作成する
SEO効果を高めるためには、リライトだけでなく新規でコンテンツを作成することも重要です。ユーザーのニーズを満たす、質の高いコンテンツ制作を目指しましょう。
Googleの検索エンジンでは、コンテンツの品質を評価する指標として「E-E-A-T(Experience-Expertise-Authoritativeness-Trust)」が重視されています。
| 評価項目 | 概要 |
|---|---|
| Experience(経験) | 実体験に基づいた独自性のあるコンテンツになっているか |
| Expertise(専門性) | 専門知識に基づいた詳細なコンテンツになっているか |
| Authoritativeness(権威性) | コンテンツ制作者が特定の分野で権威ある存在なのか |
| Trust(信頼性) | コンテンツが安全で信頼できる情報を提供しているか |
※参照:Google「品質評価ガイドライン」
たとえば同じ商品を紹介している記事があったとします。
- 記事A・・・商品の説明
- 記事B・・・商品の説明+商品を使用したレビュー
商品の紹介がされているだけの記事Aよりも、実体験に基づいた内容の盛り込まれている記事Bのほうが質の高い記事だと評価されます。
新規でコンテンツを作成する際は、E-E-A-Tも意識しましょう。

コンテンツに最終更新日を記載する
コンテンツには必ず最終更新日を記載しましょう。
最終更新日が記載されていれば、ユーザーはその情報がどれくらい新しいかを一目で判断できます。
なお、内容を更新せず、最終更新日だけを変更するような施策は意味をなしません。情報をアップデートする作業に付随し、最終更新日も更新することが大切です。
【ケース別】SEO効果の出やすい更新頻度

SEO効果を高めるコンテンツの更新頻度の目安は、下記のとおりです。
新規記事の投稿:3~5日に1回
新規記事の投稿は、ネタがあるならば毎日が理想です。とはいえ、現実的に毎日投稿は難しいケースが多いため、まずは3~5日に1回くらいのペースを目指しましょう。
更新頻度を意識するあまり、低品質なコンテンツを量産しては逆効果です。常にユーザー視点を忘れず、有益な情報を提供し続けましょう。
既存記事のリライト:投稿から3ヶ月後
既存コンテンツの場合は、投稿してから3ヶ月後を目安にリライトするのがおすすめです。検索エンジンの仕組み上、コンテンツを公開してから順位が安定するまで1~3ヶ月ほどかかるためです。結果の見えないうちからやみくもにリライトしても、効果的とはいえません。
ただし、ニュースやトレンド系など、情報の移り変わりが早いジャンルの場合はより高頻度で更新しなければなりません。更新のスパンが長くなると情報が古くなり、ユーザーからの信頼を得られなくなります。
情報の鮮度が重要なジャンルを扱うなら、目安の3ヶ月を待たずに最新の情報に更新していくことが大切です。
【まとめ】SEOにおいて更新頻度は重要

本記事では、以下の点について解説しました。
- 更新頻度とSEO効果の関係
- コンテンツ更新で得られるSEO効果
- SEO効果を高める更新の具体策
- SEO効果の出やすい更新頻度の目安
Webコンテンツの更新頻度はSEO評価に関係しますが、質の低い更新をくり返しても意味がありません。コンテンツを更新する際は常にユーザーのニーズを意識し、ユーザーにとって有益な情報を提供しましょう。
既存コンテンツをどのように更新してよいかわからない、あるいは更新のためのリソースがないという場合は、ぜひフラップネクストにご相談ください。目標から逆算した設計で、貴社の目指すゴールを確実に達成いたします。


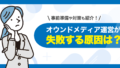
コメント